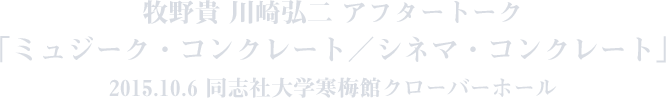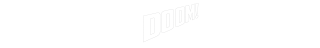「EXP/2015」最終日に同志社大学寒梅館クローバーホールにて牧野貴最新作『cinéma concret』の関西プレミア上映が行われ、上映後に牧野貴監督と電子音楽研究家の川崎弘二氏によって「ミュジーク・コンクレート/シネマ・コンクレート」と題されたアフタートークが行われた。
そのアフタートークは1時間ほどのものであったが、牧野貴という作家の表現がどのようにして生まれているのか、また『cinéma concret』がこれまでの作品からどのような場所にあるのかが語られた濃密な時間であった。
ここでは1時間ほどのトークの中から二人の話を抜粋しテキストとして再構成したものを掲載する。
牧野作品へのさらなる理解の一助となれば幸いである。
ミュジーク・コンクレート - 手続きの逆転 -
川崎(以下K):今日のトークのタイトルが「ミュジーク・コンクレート/シネマ・コンクレート」という副題がついておりまして、今日の映画が「cinéma concret」という作品だったわけですけど、そのミュジーク・コンクレート、ご存知の方も多いとは思いますけれども、現代音楽の一つのジャンルに電子音楽と言われるものがあって、その中にミュジーク・コンクレートというジャンルがあるんですが、実際に初期の作品を少しだけ聴いてみましょう。
ピエール・シェフェールの音源抜粋を聴く。
K:これは1948年にフランスのピエール・シェフェールという人が作った一番最初のミュジーク・コンクレートの中の一つですね。このミュジーク・コンクレートっていうのを始めた人たちは何をやりたかったかって言うと、普通の音楽は頭の中で何か抽象的な構想があって、こういう音楽を作ろうと思って、それを楽譜という記号化を行って最終的にヴァイオリンで演奏することによって具体性がそこに付与されると。だいたいの芸術は抽象的な構想が最初にあって、写真だったら具体的なフィルムであったり絵画だったらキャンバスだったりっていう具体的なものっていうのが最後に出来上がります。
このミュジーク・コンクレートっていうのは手続きの逆転が行われていて、今聴いていただいたように具体的な音を録音して、その具体的な録音された音を編集すると、最終的に今聴いたような抽象的な音楽が出来上がる。ちょっと僕は怪しいところがあると思っているんですけど(笑)、そういう風に主張したわけですね。で、このミュジーク・コンクレートというジャンルは今から70年ほど前にできて、今聴いていただいた曲はあまり面白くないんですけれども、ピエール・アンリという同じく1948年くらいからミュジーク・コンクレートを始めた人が今でも87歳で現役でミュジーク・コンクレートを作ってるんですね。70年経つとどれだけ洗練されるのかっていうのを、我慢してちょっと聴いてみたいと思います。
ピエール・アンリの音源抜粋を聴く。
K:ということで70年やってると、もうただのフランス音楽ですよね。聴いてて何の違和感もないというか、伝統的な音楽と何も違うところがないんじゃないかなと思うんですが、使われている音はすべて現実の音ですね。何か物を叩いたりという具体的な音。要するにヴァイオリンとかピアノのように抽象的な音ではないということですね。
で、牧野さんはおそらく自分の映画の作り方の方法論と、このミュジーク・コンクレートっていう音楽の作り方の方法論っていうのが、一致するわけじゃないですけれども、何かシンクロするようなところがおそらくおありになったんだと思うんですが、それで今回このような「cinéma concret」っていう作品が出来たんじゃないかと思うんですね。
牧野(以下M):はい。

リアルタイムの創造性 - 映画への物理的な参加 -
K:ちょっと先に「cinéma concret」を観た感想を言っておいた方がいいですかね?
M:お願いします。
K:僕は大変素晴らしい作品だと思いました。映画っていうのはさっきのミュジーク・コンクレートもそうですけれども、録音された音ですからリアルタイムの創造性というものが無いと思うんですね。で、ミュジーク・コンクレートにいかにしてリアルタイムの創造性を付与するかっていうことで、アクースモニウムっていう30個くらいスピーカーを並べてリアルタイムで音をオペレートして音に運動性を与え、テープに定着した音楽っていうものをリアルタイムで操作するっていう、そういうやり方をしてたりするんですけれども、映画っていうのは固定されたメディアで、リアルタイムの創造性みたいなものっていうのは生まれたときから無いから、多少エクスパンデッドシネマとかでリアルタイムに何かするっていうことはあるにしても、あまりリアルタイムの創造性が無いっていうことを重視されないと思うんですよね。
でも音楽っていうのは、3歳の頃から一日12時間30年間一日も休まず練習してきましたみたいな人がヴァイオリンを弾くと、その説得力とリアルタイムの創造性みたいなものってすごいものがあると思うんですよね。で、今見てて、ここまで情報量が多くなると、リアルタイムがどうのこうのとか、そういうことってあまり気にならないというか、逆にリアルタイムに何かが生み出されてるんじゃないかと。ひょっとして牧野さんがパソコンでですね、実はこれリアルタイムでフィルターかけてるんですよ、とか言われてもあり得ない話でない。
M:3D眼鏡(※1)を配ったのもリアルタイム性についての自分からのアクションです。僕はリアルタイムでフィルターかけたりというようなことはしないで、毎回完成された映像作品を上映しているんですけど、観客が映像に変化を与えることができるような、参加出来る手段っていうものをいろいろ考えていました。この方法(減光遅延方式)での3Dは僕からの押しつけでもないし、実際に皆が同じ映像を見ているという保証は無くなります。物理的に違うものを観る、体験するっていうのは、眼鏡によって映画への物理的な参加っていうか、リアルタイム性が発生していると思いました。映画も上映していないときには存在しないわけだし、上映されているときにも常に消滅し続けるっていうのは、そもそもリアルタイム性が無いとは言い切れないんじゃないかなとも思うところがあるんですけれど。
(※1) 牧野作品を3Dで見ることができるようになる片目にのみ減光フィルターの入った眼鏡。
具体映画 - cinéma concret -
K:あともう一つはこういう電子音楽っていうのは例えばテープを使った今のミュジーク・コンクレートにしても、テープに録音できるっていう新しいメディアが出来たっていうこと、音を手に取ることができる。それを音のオブジェって彼らはそう表現しますけれども、電子音楽っていうのは新しいテクノロジーが無いと生まれなかった音楽なわけですよね。逆に言うと新しいテクノロジーによって何が出来るかっていう事を追求した音楽だと思うんですけれども、今の牧野さんの映像って、おそらく従来のメディアだったら絶対出来ないと思うんですよね。映画を作るツールががどんどん進化していく中で、昔と同じ方法論で劇映画を撮るのではなく、こういった新しいデジタルなりコンピューターを使った映像表現っていうことでは、今のテクノロジーじゃないと絶対ありえない表現だと思うので、そういった点ではテープっていうメディアを使って何が出来るかっていうことを実験した人たちと近いところにあるのかなっていうのが一つです。
M:ミュジーク・コンクレートというものに興味があったのは、具体音を収集して音楽を組み立てていくというところです。僕も自分で撮影した映像を使っていて、パソコンの中だけで映像を発生させたりするのは一回もやってないんです。やりたくないんですね。部屋の中で何かを創ると気分が落ち込むばかりだし。外に行っていろんなものを大量に素材収集として撮影してきて、それを編集していく。それってミュジーク・コンクレートの初期の概念とまったく同じ事を自分はやってたのかなって考えて、それで「cinéma concret」ってタイトルが思い浮かんだんです。
ぱっと見ただのアブストラクトシネマだろって言う人がいるかもしれないんですけど、これを抽象映画として上映する事に何の意味があるのかわからなくて、わからないというか面白いと思えなくて。一つのジャンルに自分がいるっていう事を肯定した上で作品を作るっていうことがあまり良くないと思っているので、ここであえてこれを具体映画として提示する事に興味を覚えました。ただ、この作品をある特定のジャンルとして提示したいわけではなくて、映画のタイトルとして使ったっていうことです。
具体とは何か、抽象とは何かっていう問いかけですね。ミュージシャンに対しても映像作家に対しても。これで叩かれるかもしれないと思って怯えながら・・・(笑)、冗談ですけど。でも創り手としての明確なアクションを起こしたいなと思ったんです。

具体と抽象 - 具体でありながら抽象を保つ映像 -
K:先ほどのミュジーク・コンクレートの具体から抽象へっていうのは、初期の作品なんかは僕は成功しているとは思えないんです。で、先ほど牧野さんが仰ったように、必ず具体的なものを撮影して、それをものすごく多重に重ねてらっしゃるんですよね。ここまでやらないとというか、ここまでやれば具体的なものっていうものから抽象的な何かが見えるような気がするじゃないですか。ここまでやらないと具体から抽象へっていう手続きの逆転は起こらないのかなっていうのが発見ですね。
M:今までもいろいろ作品を作ってきて、最終的にノイズのような形になってぶわーって立ち上がることが多かったんですけど、でもその頃(2006-2012)から具体から抽象っていうことはずっとやっていたんです。具体から抽象に行って、抽象のあとに何があるのかっていうことはこの四、五年ずっと考えていたことで、それでまたさらに具体に戻るかって考えて。ただ、ノイズばっかりやってた人がポップに戻るみたいに、単純にもう一回そのまま具体に戻るのではなく、どんなに具体的なものが映っても抽象であることを保つ映像っていうものを作れないかなって思っていました。例えば今までは(In your star 2011)コントラストが複雑で扱いやすい建築や植物を撮影して抽象映像の中に混ぜていたんですけれど、それに抽象度を持たせるっていうことをやってみると、やっぱりどうしてもあれが窓だな階段だな人だなってわかったような気になってしまうんです。鑑賞者の想像力はそこでおしまいというか。「cinéma concret」では、たとえ具体的な何かが見えても、映像が抽象であることをを保つためにひとつひとつの映像を200重くらい重ねてるんです。そこまですると、何かがぱっと見えたらすぐに消えていってしまう。明らかに何かが見えた瞬間はあるんですけど、それが何かであるっていうことを言わないまま流れて行ってしまう。ただ、具体的な被写体を単にぱぱぱぱっとカットを割るように映像を動かせばいいじゃないかっていう事ではなくて、そこに美しさを入れたいと思って、全てフェードで繋いでいます。今自分は、具体から抽象というところから、具体でありながら抽象を保つ、というところにいると考えています。ようやくイメージそのものを自由に扱えるようになってきたような気持ちでいます。
構造 - 覚醒へ向けて -
M:ただ、デジタルで編集していると信号を一つの枠の中に入れて編集しなければならないんですけど、単純に映像の(光の)情報量が増えすぎると真っ白になっちゃうんですね。極端な話、1000回重ねたらどんな映像でも真っ白になるんですけど、そこで自分はデジタルの限界以上に何が出来るかなって考えて、そうだ映像にはネガ像というものがあるぞと。音楽にネガ像ってあるのかわからないんですけど、映像ってもともとネガからポジに焼いたりとか、制作の段階から光の反転がずっと続いていて、今回の「cinéma concret」では最終的にネガ像に落ちて行くっていうのは、映像の輝度が上がり続けて反転する、そして反転した映像が逆転して続いていきます。それを途中でやめて終わらせている、そういう構造になっているんですけど、もし途中で終わらせずに流し続けたら、最終的に映像は真っ黒になって終わるんです。そこで映画の始まりを再度流したら永遠に続く構造になっています。いつも映画を終わらせるときに、どこかで永遠に続いていて欲しいみたいな気持ちがあって、前から循環構造を取る事が多いです。
K:構造っていう点はすごく大事な点だと思います。電子音楽にしても結局はシンセサイザーによる新しい音の響きだとか、さっき聴いた初期のミュジーク・コンクレートにしても何か物を叩く音っていうのを音楽として使うっていう事で、おそらく70年前は新鮮だったと思うんですよ。新しい音響体験ですよね。こんな聴いた事の無い新しい音が聴けるというのは素晴らしいだろうっていう。でもそれだけじゃあ音楽ってあんまり面白くないんですよね。
もう一つは新しい時間体験っていうことで、音楽ってどういう構造を作っていくか、例えばミニマルミュージックみたいな反復の音楽がありますけど、あれも同じ物が繰り返されるかっていうとそうじゃなくて、ちょっとずつズレていって最初とは違うものが出てくるとか、少しずつズレて行って全然違うものが出来てくるとか、音がモワレ状に聴こえ出してくるとか。テクノのような電子音楽の反復っていうのは、陶酔していく方の反復だと思うんですね。でもこういった電子音楽で求めているのはそういった陶酔ではなくって、同じ反復でもそれがどのように変わっていくかっていう覚醒を促していく。で、覚醒を促すには聴き手の方に構造を認知することが求められるわけで、今の牧野さんの映画を見てても、音楽的なかっちりとした構造っていうわけではないけれど、ちょっとずつ変わりながら光の方に向かって、微細な変化が大きなうねりになっていくような。その辺りはかなり意識して作っていらっしゃるのかなという気はしました。
M:ミニマルミュージックには、僕は大変な影響を受けています。小さな粒子が集まって集まって想像力の源みたいなイメージが立ち上がるのが好きです。80年代以降、スティーブ・ライヒは自分の音楽をミニマルミュージックではなく、マキシマム・ミュージックだと言っていましたが、僕も自分の映画に対して同じ気持ちがあります。それは、ジャクソン・ポロックが自身の絵に対して”これはカオスでは無い”と言った時の気持ちに似ているかも知れません。反復、循環という構造は確かに重要ですが、芸術家は構造や技術を踏まえた上で、新しく作品を制作していかなければならないと考えているので、常に構造を超えた作品創りに熱中したいとは考えています。
『cinéma concret』では、現在の技術でヴィデオ内で扱える光の信号の限界と、抽象映像の限界に挑みたいと思いました。具象から抽象、そして抽象から具体的な抽象まで来たので、これからは今いる場所を出発地点として捉えて、新しいチャレンジをしていきたいと考えています。
構成:長崎隼人(DOOM!)
写真:神山靖弘
関連リンク
牧野貴HP
牧野貴作品集第二弾「Cerulean Spectacles」
川崎弘二HP









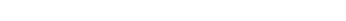
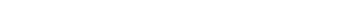
![[+]ホームページ](img/link_plus.png)